10月19日(日)
今日は、最近ずっと格闘していたNGC474の処理が、ようやく“見れる”ところまで仕上がりました。
撮影の目標は「10時間以上」。そう決めてからは、毎晩少しずつ増し撮りを重ねていきました。
最近は、Windyの衛星画像(可視画像)を見ながら雲の流れをチェックして、島のどこなら撮れそうかを見極めて動くようにしています。
晴れ間を探して島の中をあちこち転々としながらの撮影。
それでも雲に邪魔されることが多くて、撮影を中断 → 雲が流れたら再開…の繰り返し。
この作業、見た目以上に体力使うんですよね(笑)
その合間には、ミラーレスカメラの練習もしています。
ISOと絞りの関係、自分のレンズのクセなんかも少しずつわかってきて、撮るたびに発見があります。
星空も風景も、少しでも思い通りに撮れるようになっていくのが楽しくて、気づけば夢中になってました。
4日間で141×300秒、合計42,300秒(11時間45分)の露光。
ようやく使える画像を揃えることができました。
まぁここまでは“撮るだけ”なので、正直そこまで大変ではなかったのですが・・・
問題はここから。
そう、画像処理です。
NGC474の処理は、もう最初から四苦八苦。
まるで以前の「イカ星雲」のときのように、最初は何をやっても上手くいかず、全く太刀打ちできませんでした。
この銀河は、幾重にも重なるシェル(殻)構造や、細長く伸びた尾のような模様が同心円状に広がっています。
でもこのシェルがとにかく淡く、背景に埋もれてしまうんです。
最初はDrizzle画像を使って処理していましたが、どうやってもシェルが浮かび上がらない。
原因を調べてみると、Drizzleの過程で背景ノイズレベルにある淡い構造まで削ってしまっていたようです。
そこで通常画像(Drizzleなし)を使って再処理することに。
この判断にたどり着くまで、丸3日かかりました(笑)
その後、ようやくシェルの輪郭が見えてきて、次の課題は明るい核を飛ばさずに強調処理すること。
ここでは「LocalHistogramEqualization」と「HDRMultiscaleTransform」をうまく使い分けて調整。
さらに「MultiscaleLinearTransform」で細部を整えて、ようやく“見える”ところまで仕上げることができました。

今回は忘備録として、処理の流れを残しておきます。
- DynamicCrop … 画像の切り抜き
- ImageSolver
- BlurXTerminator … CorrectOnly
- SFC
- MGC
- SPCC
- NoiseXTerminator … 軽く
- StarXTerminator
(以下、星なし画像のみ)
9. PixelMathUI … SimpleStretch
10. LocalHistogramEqualization … デフォルト×2(軽め)
11. HDRMultiscaleTransform … デフォルト値
12. MultiscaleLinearTransform
- Layer1: Bias +0.1
- Layer5: Bias −0.2
(星を合成)
13. PixelMathUI …
Screen Linear or Non-Linear Stars
Star Size 0.4 Star Saturation 0.6
14. CT, HT … 明るさ・バランス調整
15. NoiseXTerminator … 最終仕上げ
まとめ
今回のNGC474は、ほんとうに手強かったです。
淡いシェル構造がなかなか姿を現してくれず、処理を進めるたびに何度も行き詰まりました。
ストレッチすれば背景が荒れ、ノイズを抑えれば構造が消える──そのせめぎ合いの中で、
どうやったら「淡さを保ちながら存在感を出せるのか」をずっと探っていました。
それでも、少しずつ形が見えてくる瞬間があって、そのたびに小さな達成感を感じながら進めていきました。
最初は何も見えなかった画像の中から、うっすらと円を描くような模様が浮かび上がってきたとき、
「あ、いた…!」と声を出してしまったほどです。
処理を終えてあらためて感じたのは、淡い天体ほど“丁寧さ”がすべてだということ。
ほんの少しの設定の違いや工程の順序で、仕上がりが大きく変わってしまいます。
同時に、失敗の一つひとつが学びになり、次の撮影や処理に繋がっていく。
そういう積み重ねが、この趣味の一番の面白さなのかもしれません。
まだまだ満足とは言えない仕上がりですが、今回の試行錯誤を通してたくさんの発見がありました。
時間をかけてじっくり向き合ったぶん、このNGC474は特別な一枚になりそうです。
ビクセン(Vixen) セレストロン 天体望遠鏡 NexStar 4SE Maksutov 日本語説明書 ビクセン正規保証書付き 36019 CELESTRON 11049
只今、価格を取得しています。
(2026年1月20日 02:48 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)SIGHTRON サイトロン 天体望遠鏡 初心者 地上 天体 兼用 スマホ撮影 MAKSY GO 60
只今、価格を取得しています。
(2026年1月20日 02:48 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)ビクセン(Vixen) セレストロン 天体望遠鏡 NexStar Evolution 8 SCT 日本語説明書 ビクセン正規保証書付き 36024 CELESTRON 12091
只今、価格を取得しています。
(2026年1月20日 02:48 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)Unistellar Odyssey Pro スマート天体望遠鏡 ユニステラ オデッセイ プロ 日本正規品 3年保証
只今、価格を取得しています。
(2026年1月20日 02:48 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)SIGHTRON サイトロン 天体望遠鏡 初心者 地上 天体 兼用 スマホ撮影 MAKSY GO 60 ターコイズ NB1040010006
只今、価格を取得しています。
(2026年1月20日 02:48 GMT +09:00 時点 - 詳細はこちら価格および発送可能時期は表示された日付/時刻の時点のものであり、変更される場合があります。本商品の購入においては、購入の時点で当該の Amazon サイトに表示されている価格および発送可能時期の情報が適用されます。)







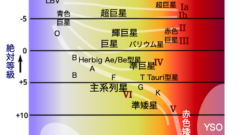
コメント